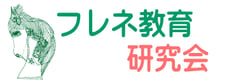地域と“公”の協同でつくる『幼保小の架け橋プログラム 』―沖縄県八重瀬町の実践と連携―
日 時:12月21日(日)13:00~16:00
オンライン開催
参加費:一般800円、学生無料、会員無料
内 容: 先駆的な幼小連携の実践事例である沖縄県八重瀬町『架け橋プロジェクト』について、行政、公立園の立場からお二人の先生に保こ小連携の取り組みや実践をご紹介いただきます。
事例をもとに、琉球大学の塚原先生に幼小連携の視点から、東洋大学の瓦林先生にフレネ教育 の視点から解説していただきます。
現場の先生方はじめ「今の教育ってこれで良いの?」と思うすべての方々、ぜひご参加ください!
八重瀬町の「架け橋プログラム」
2020年に開始された『八重瀬町保幼小連携プロジェクト』では、学校園間の接続意識の違いが課題とされました。 そこで、子どもの姿を共有する公開保育や授業を通じて、保育者や教師が対話を重ね、保育・授業の改善や連携の進展が図られました。
報告者紹介
国吉和美先生
重瀬町教育委員会保こ小連携アドバイザー。町内の公立幼稚園の教諭として、38年間の保育経験後、保こ小連携コーディネーターを経て、現職。教育委員会と児童家庭課、現場の先生方との橋渡しをしながら、研修企画や支援を行っている。特に、町内の保育園、こども園の先生方とは、子どもの見取りや指導計画、環境などについて一緒に考え、時に子どもたちと一緒に遊ぶことを大事にしながら、保こ小の先生たちと分かち合う場を行政としてつくれるように取り組んでいる。
佐久間奈津子先生
八重瀬町立ぐしかみこども園5歳児担任。町立の公立幼稚園教諭として15年間勤務。令和5年度よりこども園に移行し5歳児担任として3年目。子どもと一緒に遊びながら、“発見や驚き、喜び”など心の動きを大切にしながら、園の職員とチームで子どもの育ちを支えている。
コメンテーター紹介
塚原 健太先生
琉球大学教育学部准教授。専門はカリキュラム論、教育史。沖縄に赴任してから八重瀬町をはじめ、県内の幼小接続や生活科・総合学習の実践に携わる。保育・教育を担う先生方とともに子どもや実践について対話しながら、子ども主体の保育・教育の在り方を考えている。本来の専門である大正新教育カリキュラム史研究からは、教師の手による創造的な実践を可能にする条件を探る。
瓦林亜希子先生
東洋大学文学部教育学科准教授。専門は教育方法学、日仏比較教育学。日仏の教育実践研究を通し、子どもの自由な自己表現や探究的な学びをどう保障するかについて、幼児教育から中等教育までを分析している。特にフレネ教育について研究し、子ども中心・学習者主体の学びを実現するための哲学と方法・技術、さらに近代教育制度の問題点と現代学校の可能性と改革の方向を探っている。