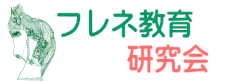フレネ教育とは?
セレスタン・フレネ

(Celestin Freinet, 1896-1966年)
フランスの片田舎の教師だったフレネは、子どもたちの世界からかけ離れた学校の姿に疑問をもちました。そして「手仕事を学校に」「教室に印刷機を」などのスローガンと共に、学校の現代化運動をはじめます。この運動は、ヨーロッパ、南米、アフリカなど世界38カ国余りの国々にひろまり、レッジョ・エミリアの保育や、イエナプラン教育など、その後のオルタナティブ教育の発展にも大きな影響をもたらしました。
このフレネの考えを取り入れつつ、目の前の子どもたちと共に様々な教育実践をつくっていく。これを私たちは「フレネ教育」と呼んでいます。フレネ教育は固定されたメソッドではなく、開かれた教育技術なのです。
フレネ教育のキーワード
私たちにできること
1、実践してみる
現在の指導要領に基づいた学校の中でフレネ教育を実践することは難しいかもしれません。しかし、フレネ教育のエスプリを生かして、子どもの側から授業や学級をつくっていくことはできます。ここでは私たちにできる実践方法を紹介します。
2、学習する
フレネ教育が日本で実践された例は、これまでもいくつかあります。それらの実践家の本からヒントを得ることもできるでしょう。また、フレネ自身が書いた本の訳書や、研究者による書籍もあります。ここではブックリストをあげておきます。
フレネ教育研究会 事務局
〒173-0862
東京都板橋区加賀1-18-1
東京家政大学 児童教育学科 初等教育第7研究室 結城孝雄
TEL・FAX : 03-3961-5594